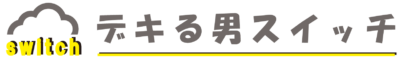挨拶は人間関係を築く上でも潤滑油になります。
この挨拶の「こんにちは」と「こんにちわ」、どっちが正しいのか、あなたは分かりますか?
知らないと恥ずかしい思いをするかもしれません。
そこで今回、この「こんにちは」と「こんにちわ」どちらが正しいのかを紹介します。
スポンサーリンク
「こんにちは」と「こんにちわ」どちらが正しいの?

「こんにちは」と「こんにちわ」、インターネット上ではどちらもよく見かけます。
普段、何気なく使っている挨拶言葉ですが、意識して考えてみると、どちらが正しいのか自信が無くなりませんか?
「こんにちは」が正しい

じつは、「こんにちは」が正解です。
「こんにちわ」は間違いですから、使わないように注意しましょう。
昭和61年7月1日に内閣府から告示された「現代仮名遣い(内閣告示第1号)」でも、「こんにちは」が正しい使い方ですよ!と示されています。
また、広辞苑や国語辞典といった辞書にも「こんにちわ」の表記はありません。
載っているとしても、誤用としての表記だけです。
「こんにちは」が正しい理由

では、なぜ「こんにちわ」ではなく、「こんにちは」になったのでしょうか?
その理由を語源から見てみたいと思います。
昔の日本人は、次のような挨拶をしていました。
◆ 今日(こんにち)は、ご機嫌いかがですか?
◆ 今日(こんにち)は、天気が良いですね!
この挨拶の後半部分が省略され、「今日(こんにち)は」の部分だけが挨拶として残りました。
そして、「今日」と言う漢字は「きょう」とも読めてしまうため、「こんにち」とひらがなで表記するようになり、今の「こんにちは」になったのです。
つまり、「こんにちは」は次の3つの過程で変わってきたのです。
1.「今日(こんにち)はご機嫌いかがですか?」
2.「今日(こんにち)は」・・・後半が省略された
3.「こんにちは」・・・読みやすいようにひらがなに変わった
スポンサーリンク
なぜ「こんにちわ」と間違えるの?
では、どうして「こんにちわ」という間違いが生まれたのでしょうか。
諸説ありますが、今回はその理由を3つ紹介します。
昔は「こんばんわ」が正しかったから

昔は「こんばんわ」でも遣い方として正しかったことから、勘違いして「こんにちわ」を遣うようになった人がいる、というのが1つ目の理由です。
「は」と「わ」、どちらを使うのかは、内閣府によって告示される「現代仮名遣い」で決められています。
じつは、この歴史に1つ目の原因があるのです。
昭和21年に告示された現代仮名遣い
昭和21年11月16日に公示された「現代仮名遣い(内閣告示第33号)」により、内閣府から発音通りのかな遣いが推奨されました。
この時、「こんにちは」と「こんばんわ」が、両方とも正しい言葉遣いとして使われるようになりました。
昼の挨拶は「は」であり、夜の挨拶は「わ」なんですね。
「こんにちは」が「こんにちわ」と間違って使われるようになったのも、この頃からと言われています。
「は」と「わ」を昼と夜で使い分けるのが難しかったようですね。
昭和61年に告示された現代仮名遣い
このような混乱を経て、昭和61年7月1日に告示された「現代仮名遣い(内閣告示第1号)」によって、「こんにちは」「こんばんは」が正しい使い方ですよ!と内閣府から示されました。
これにより、「こんにちは」「こんばんは」は共に「は」を遣うことで統一されたのです。
このように時代が変わると共に、現代仮名遣いの「は」と「わ」の使い分けが変わったことが、「こんにちわ」を生む1つの理由として考えられます。
日本は「和(わ)」の国だから

日本は昔から「和(わ)」を重んじる国民性があり、「は」という文字よりも「わ」という文字に親しみがあるから、というのが2つ目の理由です。
昔、歴史で習った魏志倭人伝にも、日本は倭(わ)の国として登場します。
日本を「大和(やまと)」と書きます。
日本風のことを「和風(わふう)」と言います。
このように、日本人は昔から「わ」という言葉に親しみを感じているから、間違って「こんにちわ」と無意識に遣ってしまうのかもしれません。
声に出すと「わ」だから

「こんにちは」を音声にすれば、「コンニチワ」だからというのが3つ目の理由です。
確かに、「コンニチハ」と言う人はいませんよね。
シンプルですが、これが理由で間違っている人は多いのではないでしょうか?
その他の言葉
挨拶には「こんにちは」だけではなく、その他の言葉もきちんと意味があります。
ただの社交辞令ではなく、挨拶の言葉の意味を知って、正しく挨拶をするようにしましょう。
おはよう(お早う)

「おはよう」は朝の挨拶ですね。
この言葉は昔、次のように使われていました。
◆ お早(はよ)うお越しで(お元気でなによりです)
自分よりも先に来ていた人に対する声かけとして使われていたのですが、後半部分が省略され、「おはよう」だけが残ったという歴史があります。
さようなら(然様なら)

「さようなら」は別れの挨拶です。
この言葉は昔、次のように遣われていました。
◆ 然様(さよう)ならば、お別れですね
◆ 然様(さよう)ならば、ご機嫌よろしく
「さようなら」はもともとは、別れの言葉の前に言う言葉だったのです。
「然様ならば」は「そうであるなら」という意味になります。
しかし、これも後半部分の、もともとの別れの言葉は省略され、前半部分の言葉「さようなら」だけが別れの意味を持って残ったのです。
たまに「左様(さよう)ならば」という表記を見かけますが、正確には「然様」です。
すみません(済みません)

「すみません」は、感謝する時と謝罪する時、両方遣います。
この言葉は、感謝の意味では「たいしたお礼もできずに、自分の気持ちがこれでは済みません」というように遣われています。
逆に、謝罪の意味では「大変申し訳なくて、自分の気持ちがこれぐらいでは済みません」というように遣われています。
「すみません」とは自分の気持ちが「済まない」という意味なんですね。
まとめ

今回は普段、何げなく遣っている「こんにちは」という挨拶の正しい使い方を紹介しました。
正しくは「こんにちは」であり、「こんにちわ」は間違いです。
この「こんにちは」は次のように、時代とともに形を変えてきました。
1.「今日(こんにち)はご機嫌いかがですか?」
2.「今日(こんにち)は」・・・後半が省略された
3.「こんにちは」・・・読みやすいようにひらがなに変わった
なぜ間違えるようになったのか、これには諸説ありますが、今回は3つの理由を挙げました。
1.昔は「こんばんわ」が正しかったから
2.日本は「和(わ)」の国だから
3. 声に出すと「わ」だから
このように歴史背景とセットで覚えると、忘れにくくて良いのではないでしょうか。
きちんと意味を理解して、正しい挨拶言葉を遣っていきたいですね。
こちらの記事も合わせてどうぞ ↓