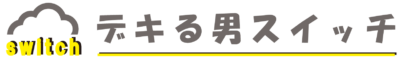皆さんはギフテッドという言葉を聞いたことがありますか?
まだあまり知られていない言葉かもしれないですが、ギフテッドの子どもに接したことはおそらく誰でもあると思います。
今回は、そんなギフテッドの子供が持つ悩みや、どのように育てれば良いのかということについて紹介します。
スポンサーリンク
ギフテッドとは

日本ではまだまだ馴染みのないギフテッドという言葉ですが、アメリカではすでに定着している概念で、ギフテッドといわれる子ども達への対応も確立されつつあります。
ギフテッドとは、ひと言でいうと知能指数(IQ)がずば抜けて高く、計算力などの学力が群を抜いているだけでなく、感受性も強いのが特徴です。
IQが高いとか低い、とよく言われますが、およそ8割の人は80~120くらいのIQであり、130を超えるとギフテッドだとされています。
ただ、最近ではこの数値だけで判断せず、多様な審査方法が採用されています。
ちなみにIQは、「精神年齢 ÷ 生活年齢 × 100」で計算されます。
例えば、6歳の子どもが6歳の精神年齢を持っているならIQは100ですが、5歳の子どもが6歳の子どもの精神年齢ならIQは120になります。
アメリカでは子どもの2~6%がギフテッドであるといわれていますので、決して珍しい存在ではないのです。
しかし、日本ではギフテッドへの理解が進んでいるとは言えない状況なので、学校生活にもうまく馴染めずに、浮いてしまっている子どもも少なくないとされています。
スポンサーリンク
ギフテッドの悩み

一般的に、頭が悪くて悩むことはあっても、いいことでの悩みなんてないのでは?と思われがちです。
しかし、ずば抜けて頭がいいということは、本人にとって必ずしも幸せなことではないようです。
同年代の子と話が合わない
大人と子どもの話が合わないのは分かると思いますが、ギフテッドは子どもであっても知能がずば抜けて高いので、子ども同士、話が合うわけがありません。
同年代の子どもとうまくやっていくことが出来ずに、クラスでは浮いた存在になりがちです。
共同作業が出来ない
集団で何かするということがあまり得意ではありません。
自分の失敗のみならず人の失敗にも厳しいところがあり、単純な作業も得意ではないので、グループで共同作業をするといったことが苦手です。
学校の授業がつまらない
学校はどちらかというと、平均点の子ども、もしくはそれよりやや低めの子どもに合わせて授業をします。
当然ですが、落ちこぼれを作らないためです。
ギフテッドの子どもはずば抜けてIQが高いので、教科書なんて1度読んだらたいてい頭に入ってしまいますし、学校でやる程度の、自分の実年齢に合わせた授業では、簡単すぎてまったくおもしろくないのです。
勉強が苦手な人から見たらうらやましいと思うかもしれませんが、それはギフテッドの子にとっては苦痛でしかありません。
それが授業に集中できない、授業中に内職してしまうなどの行動になってしまいます。
人の気持ちがわかりすぎる
ギフテッドの子どもは、感受性が非常に強く、自分の感情も強く感じますが、友達の気持ちや感情も同様に強く感じ取ってしまいます。
ですから、相手がすべてを話す前に、その気持ちやどうしたいのかということが先に分かってしまうのです。
何でも先に分かってしまうというのは決して楽なことではありません。
他者に批判的になってしまう
自分だけでなく相手にも完璧を求めるあまり、他者に対して批判的になってしまうことがあります。
それは同年代の子どもの間で浮いてしまう原因になります。
周りから理解してもらえない
IQが高いことが分かっても、なぜそのような行動や言動を取るのか、といったことが周りの友達のみならず、家族からも理解をしてもらえないことがあります。
これは大きな心理的ストレスになり、問題児扱いされていることがトラウマになることも。
大人になってからもそのトラウマを抱えたまま、うつやノイローゼになってしまう人もいます。
ギフテッドの育て方

ギフテッドの子がその才能を伸ばし、のびのびと生きていくにはどうすればいいか、育て方や接し方についてお話したいと思います。
学校以外の楽しみを見つける
学校の勉強がつまらない場合、インターネットやオンライン教材で幅広い分野の勉強ができます。
ギフテッドの子は知的好奇心が旺盛なので、それを満たしてあげるような勉強の材料があれば、学ぶこと自体がもっと楽しくなるでしょう。
その子の才能を伸ばす
絵を書くことが大好きだったり、音楽が好きだったり、学校の勉強以外に没頭できるものがあるなら、その才能を伸ばして上げるのもひとつの方法です。
たとえば、音楽なら一緒に演奏するなど、共同作業の練習にもなります。
自分が好きなことなら、誰かと一緒にやるのも苦にならないことが多いのです。
一緒に学ぶ
子どもの疑問、質問をしっかり受け止めましょう。
まだ子どもなんだから、そんなことを勉強しなくていい、などと突き放さず、どんなことを聞いてきてもいったんそれを受け止めます。
一緒に調べものをするのもいいでしょう。
大人が自分のことを受け止めてくれている、という安心感を得ることで気持ちも行動も落ち着いてきます。
感受性の強い自分を肯定する
感受性が強いということは、決して悪いことではありません。
今の世の中では行きづらさを感じることもあるでしょうが、一つの個性として捉えましょう。
人が気づかないことにも気づけるということはいいことなんです。
今の自分をそのまま受け止められるように、「そんなことで泣かない!」「いちいち怒らないの!」と、感情を否定しないで、まずはその気持ちを受けて止めてあげましょう。
まとめ

日本は協調性や周りのとの和を保つことが重要視する社会であるため、ギフテッドの行動が「問題行動」とされてしまうことも少なくなく、発達障害と混同されてしまうこともあります。
しかし、それでは生きること自体に希望を見いだせなくなってしまいます。
その子の才能をうんと伸ばしてあげられるように、家族や周囲の大人達がギフテッドの個性を理解し、適切な対応を取ることが望まれます。
こちらの記事も合わせてどうぞ ↓